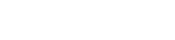vol.215 個人の意欲と能力を最大限生かせる社会の実現
皆様、こんにちは。アカウンティングワークスの花房です。
先月21日、日本初の女性首相となった高市早苗内閣が発足しました。株式市場は、総裁選前の4万5千円台から約1ヶ月で、5万2千円台と、15%近く上昇しています。生成AIの過熱相場もあると言われていますが、高市政権への期待の表れでもあると思います。
そのような高市政権の政策の1つに、労働時間規制の緩和の動きがあります。残業時間に上限規制を設けている働き方改革関連法は、施行から5年を過ぎた時点でその見直しが検討されています。コロナ禍を経て、リモートワークの普及や残業時間の削減など、以前と比べて働き方はずいぶんと変わりました。
一方で、人口動態での現役世代の減少や、働き方改革で1人あたりの就業時間が減少した結果、中小企業を中心に労働力の確保に対する不満が生じています。
今年の5月に、自由民主党中小企業・小規模事業者政策調査会から石破首相へ、「内外経済の転換期における地域経済の好循環の実現」と題された提言が行われました。その中で、『…やりがいや所得向上の観点からも、「もっと働きたい」という働き手や、仕事を通じて成長したい若者、自己研鑽や技能伝承・研修のために勤務時間以外の時間を使いたい働き手が存在する。そのような方にとっての「働きたい改革」の位置づけを、あくまでも働き手の健康をしっかり確認することを前提に再検討し、「働きたい人が働ける社会」とするための「働きがい改革」に繋げて行くべきではないか。…』ということが提起されています。
今回は、働き方改革関連法施行から5年が経ち、見直しが議論されていることから、改めて「働き方改革」がどうあるべきか、今後の日本の永続的な成長の観点から考えてみたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.働き方改革がなぜ必要だったか
----------------------------------------------------------------------
働き方改革関連法の背景として、労働人口の減少により、長時間労働による従業員の健康阻害や、仕事と家庭の両立、すなわち育児や介護を働きながら無理なく行えること、また、正規社員と非正規社員の不平等をなくすと言ったことがありました。そして、残業の上限規制の実施により、時間外の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満とすることや、年次有給休暇の取得の義務化、同一労働同一賃金の導入等が行われました。
働き方改革とコロナ禍、両方の影響があると思うため、一概には言えませんが、厚生労働省の公表している年間総労働時間の推移によると、一般労働者(パートタイム以外)の年間総労働時間は、1994年から2017年までは年間2020~2030時間前後でほとんど変化なく推移していましたが、働き方改革関連法が施行された(コロナ禍初年度でもありますが)2020年は1925時間と、この30年間で最低の労働時間となり、その後2024年は1946時間と、この5年間で1900時間台半ば程度で定着しているようです。
コロナ禍という特殊事情が重なったとは言え、働き方改革関連法は長時間労働抑制に一定の効果があったように見受けられます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.現在の潮流
----------------------------------------------------------------------
日本経済新聞社とテレビ東京が先月24〜26日に行った世論調査では、現在の労働時間規制の緩和の是非に対して、賛成が64%で、反対の24%を大きく上回ったとのことです。特に、39歳以下は7割半ば、40・50代は7割が賛成と、比較的若手、現役世代で規制の緩和に賛成の割合が高かったそうです。
ワークライフバランスを重視するといわれてきた若手が労働時間規制の緩和に対して賛成の割合が高いことは意外ではありますが、実際に、若手ではもっと働くことで早く成長したいと願う社員もいますし、ハードルの高い仕事を残業してでもこなしたいと思っても、若手に振られる仕事は物足りないレベルのもので、定時になると帰らされる、という話も聞きます。『多様性』という言葉が一般的になった現在において、1人1人仕事に対する働き方の要望は様々であり、画一的な仕組みを当てはめることは、若者のやる気を削いでしまうことも懸念されます。
経営学者のフレデリック・ハーズバーグが提唱した「二要因理論」によると、仕事の不満を解消する要因は「衛生要因」と呼ばれる一方で、満足度を高める要因は「動機付け要因」、と言われます。働き方改革関連法はどちらかと言うと、「衛生要因」を高める施策であったのではないでしょうか。
先日、あるクライアント先で、会社としてはなるべく残業を抑えるように指導しているにもかかわらず、誰よりも遅くまで残って仕事をしている方がいて、しかし、営業成績はトップでクライアント先からの信頼も厚い方がいる話を聞きました。しかし、本人は営業成績を上げたい訳ではなく、責任感から自分が納得いくまで仕事を仕上げる結果、長時間労働になってしまうとのことでした。
これからは、仕事に対してのやる気を高める「動機付け要因」の施策も行うべきであり、従業員の健康に配慮することが前提ですが、働きたい人に十分働いてもらうことも、人によっては仕事に意義を感じられる動機付けとなります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.働くということ
----------------------------------------------------------------------
働くことに対する考え方は、国・地域により、時代により異なります。西洋では労働は罪を償う罰と言う考え方もあり、日本では古来より、神聖で尊い行為という考え方もありました。一方で、生活するための糧であることは否定出来ません。しかしながら、せっかく働くからには仕事が楽しくある方が良くて、趣味と実益を兼ねるとまでは言いませんが、やりがいを持って取り組めるようにしたいものです。
仕事を作業として嫌々こなすことからは、創造性もイノベーションも起きないと思います。
私の中高の先輩で現在70代半ばの方は、今でも現役の研究者ですし、今年退任する70代のクライアント先の専務は、2~3年前に、「今が一番、仕事が面白い」と仰っていました。いずれもお話すると、色んなことに興味を持っておられ、若々しさを感じられます。
働く時間だけでなく、いつまでも働けることを含めて、多様な働き方を容認する仕組み、価値観が多様化していることに合わせて、個々人に合わせた働き方があっても良いと思います。また、ライフステージごとに、働き方や仕事に対する優先順位を変える、場合によっては職種を変えるということがあってもよいと思います。ただ、それを実現するには個人が力をつけることが必要であり、そのためにはリスキリングや、リカレント教育も重要となってきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 4.おわりに
----------------------------------------------------------------------
今年のノーベル賞では、日本人としてノーベル生理学・医学賞に大阪大学特任教授の坂口志文氏が、化学賞に京都大学特別教授の北川進氏が選ばれました。研究者の方はそれこそ、四六時中研究のことを考えている方も多いでしょうし、研究によっては毎日記録を取る必要もあると思います。どこまでが仕事でどこからがプライベートか区切りがつきにくく、働き方が一般の方と異なるかもしれません。
働き方改革を単なる「衛生要因」から「動機付け要因」へと後押しする仕組みにするためには、労働環境的な施策だけはなく、人財を育てる教育システム、少子化対策や介護問題を解消する育児や介護制度、リスキリングやリカレント教育を促す仕組み、税制と言った様々な社会制度を同時に改革していく必要があると思います。
日本の今後の成長を支える鍵として、イノベーションを起こさなければならないことは、政府も言っています。そのための1つとして、先端技術の開発が重要であり、文部科学省が全国の高校でスーパーサイエンスハイスクール(SSH)を指定し、科学技術人材の育成に取り組んでいます。実は、私の母校もSSHに指定されていて、在校時は文系と理系のクラスは同数で、全体的に文系の人数の方が多かったように思いますが、今では理系のクラスの方が多くなっています。
このような取り組みから、優秀な人材が世の中に輩出され、仕事においてもやりがいを持って働けることで、日本を成長に導くイノベーションが生まれることに期待したいものです。