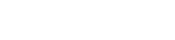vol.213 内部監査ガバナンスについて考える
ビズサプリの久保です。会期終了間近の大阪・関西万博に行ってきました。4月の来場者は1日平均8万人台だったのが、9月には20万人を超える日があり、筆者が行った日は平日にもかかわらず17万人ぐらいでした。隣ではIRの建設が始まっていました。
今回のメルマガでは、内部監査に対するガバナンスのあり方について考えてみました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.内部監査の監督は誰がしているのか
----------------------------------------------------------------------
内部監査はリスク管理のカナメですが、それが有効に機能していることを誰が監視監督しているのでしょうか。内部監査部門長任せになっていないでしょうか。ほとんどの会社が、内部監査を社長直轄としていますが、多忙な社長がどれだけ内部監査の実効性に配慮できているでしょうか。
社長直轄では、経営トップが関与する不正等の指摘ができないという課題もあります。コーポレートガバナンス・コードにおいて、内部監査による取締役会への報告が必要とされたのは、その問題意識があるからです。
ある社外取締役から、「当社の内部監査はあまり役に立っていない」といったお話を聞いたことがあります。そうであれば、取締役会が内部監査の機能向上に責任をもって対応することが必要です。
内部監査を有効に機能させるためには、内部監査の品質に留意しなければなりません。筆者は、内部監査の品質確保のための要素は次の4つであると考えています。内部監査ガバナンスは、この4つの要素の基礎となるものです。
1)内部監査人の資質
2)内部監査の手法
3)必要十分な内部監査人数
4)内部監査の品質管理
「内部監査があまり役に立っていない」ことは、企業のリスク管理上大きな問題です。最近発覚した製品検査偽装、点呼不備、セクハラ・パワハラ、個人情報の流用などの不祥事は、品質の高い内部監査を実施していたら早期に発見できていた可能性が高いと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.取締役会が所管する内部監査
----------------------------------------------------------------------
日本では監査役(会)設置会社が多いですが、東証プライム上場会社では、監査等委員会設置会社数が監査役会設置会社を超え、指名委員会設置会社と合わせると過半数(53%)になりました。また、社外取締役が過半数の会社が26%、3分の1から半数の会社は72%になりました(「上場企業のコーポレートガバナンス調査」日本取締役協会2025 年8月1日)。
この実態を見ると、従来の監査役会設置会社におけるマネジメントボードから、社外取締役が監視監督するモニタリングボードに移行していることが分かります。
マネジメントボードの取締役会は、経営と監督が分離されていないため、社長が内部監査を直轄することが当然の帰結であったと思われます。
モニタリングボードになれば、経営を監督する観点から、内部監査を経営側に置くのではなく、経営者を監督する取締役会が内部監査を所管することが最も良いということになります。
すなわち、モニタリングボードでは、取締役会において監査を担当する監査(等)委員会が内部監査を所管するのが当然の帰結ということになります。
社外取締役が過半数である監査(等)委員会が指揮監督する下で内部監査を実施することにより、冒頭の4つの要素に配慮した内部監査を監督する体制が確立できます。内部監査に対するガバナンスの観点では、これが理想的な体制であるということができます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.監査役会設置会社の場合
----------------------------------------------------------------------
監査役会設置会社の場合は、議論はありますが、監査役会と内部監査の関係は連携であり、指揮命令関係にはできないと整理されています。これは、監査役会は取締役会の外から内部監査を含む内部統制システムを監査する立場であるとの考え方に基づいています。
実際上、監査役会設置会社において、監査役会が内部監査に指示できるとしている会社はありますが、監査役会直轄としている上場会社はありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 4.内部監査部門の人事はどうするか
----------------------------------------------------------------------
内部監査の所管を監査(等)委員会であるとした場合でも、内部監査部門の人事は誰がするのでしょうか。社員である以上、採用、異動、人事評価などは人事部門が実施することになるでしょう。
監査(等)委員会は、会議体でありこれらの業務を実施することはできません。人事部門が内部監査の人事を管轄すると、人事部を対象とした内部監査の際に問題があるため、社長が内部監査部門の人事を統括するしかありません。
すなわち、社長は組織上内部監査を所管し、監査(等)委員会は監査職務上内部監査を所管する体制ということになります。
さらに、社長による人事権の行使により、内部監査に影響を与えることを防止するため、内部監査の人事(採用・評価・異動)には、監査(等)委員会の事前の同意が必要であるとすれば万全です。
実は、米国の上場会社ではこの体制が最も多いパターンです(米国ではCEOではなくCFO所管が多いようです)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 5.監査(等)委員会直轄が多くない理由
----------------------------------------------------------------------
日本では、残念ながら監査(等)委員会が内部監査を直轄する体制への理解が進んでいません。日本内部監査協会による調査では、内部監査が監査(等)委員会に直属する会社は636社中22社(3.4%)でした(2023年監査白書)。調査対象から監査役(会)設置会社を除くと、監査(等)委員会設置会社の中では10%程度になります。
監査(等)委員会設置会社でも従来どおりの社長直轄の会社が多いのは、監査役会設置会社から移行したものの、モニタリングボードの趣旨が十分理解されておらず、また内部監査の品質に十分な配慮を行っていない会社が多いためではないかと思われます。
モニタリングボードにおいて、リスク管理体制を強化するためには、内部監査の所管を監査(等)委員会とするのがベストです。