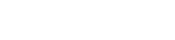vol.211 貿易と関税
皆様、こんにちは。アカウンティングワークスの花房です。
昨年、新1万円紙幣の「顔」として採用された渋沢栄一氏ですが、最近、遅まきながらその伝記である、「雄気堂々(上・下)」(新潮文庫)を読みました。渋沢栄一が生きた、1840年から1931年は、江戸時代末期から明治維新を経て、日本が鎖国をやめ、近代国家へ移行していく中でした。渋沢は生涯で500社にも及ぶ企業の設立に関わったということで、「日本資本主義の父」と言われています。本を読んでの私の感想としては、企業を設立したり、その支援をしたりしたことも功績でしょうが、それよりも、役人と実業家の両面で、近代日本の仕組みづくりに大きく関わっていたことに驚きを覚えました。
ところで、今年は第2期トランプ政権において、4月に発表した新たな関税政策、いわゆるトランプ関税が、大きな話題となっています。関税とは、国内産業の保護や政府の収入を目的として、輸入品に対して輸入国が課す税金です。渋沢栄一は、明治維新後の新政府において、現在の財務省主税局長に相当する『租税正(そぜいのかみ)』に任命されましたが、この時代は、1858年締結の日米修好通商条約以降、関税自主権のない不平等条約の中にあり(1911年の新日米通商航海条約により、関税自主権を回復)、日本の関税率が5%であるのに対して、アメリカ側は30%程度の関税率であったと言われています。
国と国の間での商品やサービスの取引が貿易ですが、貿易には、関税や輸入への制限を最小限にする「自由貿易」と、相対する概念で、関税や非関税措置で制限をかける「保護貿易」があります。第二次世界大戦以降、1947年のGATT(関税および貿易に関する一般協定)から1995年設立のWTO(世界貿易機関)を経て、世界は自由貿易が促進されてきました。しかしながら、トランプ関税により、アメリカは一気に保護貿易寄りになったと見えます。
今回は、関税について考えてみたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.114年前に戻る?
----------------------------------------------------------------------
企業は、国内や国際間で取り決められたルールの中でビジネスを行いますが、そのルールを決めるのは国であり、国が定めるルールの良し悪しで、企業や経済が発展するかどうかの枠組みが決まると言っても過言ではないと思います。その国際間のルールの1つが関税です。世界恐慌後に先進国が自国産業の保護を目的として、関税率引き上げや輸入制限等、保護貿易政策を強化したことが第2次世界大戦の開戦の一因とも言われています。
保護貿易は国同士の経済を分断して対立を深めることになりかねません。そのため、第二次世界大戦後は、GATTを経てWTOが設立され、関税率が引き下げられて来た他、国際規格の使用や、ダンピング輸出の防止のための関税や、輸出補助金の禁止、国内産業に重大な影響を与えるような輸入急増の場合のセーフガード、知的財産権に関するルール等、公正な自由貿易が行われるような枠組みが作られてきました。
さらに最近は、自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の締結により、貿易だけでなく投資や人的交流など幅広い分野をカバーすることで、より貿易を活発化する流れにありましたが、4月2日にトランプ大統領が発表した相互関税は、このような世界の潮流に逆行する政策と言えます。
なお、2025年7月27日付の日経新聞記事によると、8月1日に引き上げる相互関税により、アメリカの平均関税率は20%に上昇し、トランプ政権発足時の2%台から急増することになります。20%を超えるのは114年ぶりとのことで、西暦1911年以来ですから、奇しくも、日本が関税自主権を取り戻した明治時代に遡ることになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.トランプ関税の合意
----------------------------------------------------------------------
アメリカのトランプ大統領が、今年の4月2日にすべての国・地域に10%の一律関税をかけ、その上で日本のような高い貿易障壁を持つ相手国に対して相互関税(日本は24%)を課すことを発表し、90日間の猶予期間を設ける間に、各国はアメリカと関税交渉をしていました。日本は、7月22日に相互関税を15%とすることで、日米間で合意しました(8月7日発動)。しかしながら、自動車関係の引き下げ時期は決まっていないことや、半導体、医薬品等について分野別の関税が課される可能性もあり、先行きに不透明な部分も残っているようです。
また、この日米の関税合意と並行して、最大5,500億ドルの対米直接投融資の資金枠を約束しました。これにつきトランプ大統領は、おそらく史上最大の取引だと言っているとのことです。今後、アメリカが製造会期で国内工場を建設する際に、日本は資金枠の範囲で、当融資を実行することになると考えられます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.渋沢栄一の教え
----------------------------------------------------------------------
渋沢栄一は、日本に株式会社を導入した第一人者であり、第一国立銀行(現在のみずほ銀行)を設立した他、富岡製紙工場や王子製紙の前身の製紙会社、日本郵船の前身の会社等、日本のかつての基幹産業の中心となる会社の設立に関わりました。
一方で、大蔵省時代に渋沢栄一の提案で、調査研究により旧制度を改革し、新制度の立案をする特別の組織である「改正掛」を発足し、渋沢栄一がその長となりました。改正掛では、国の根幹となる貨幣制度や税制をどうするかに始まり、全国の測量、度量衡の単位を尺貫法とともにメートル法を公認したり、鉄道の敷設(新橋横浜間)や、太陰暦に代えての太陽暦の採用したり、地租改正(税収を、豊凶により左右される年貢から、地価に対する課税に代えることで安定化)等、近代国家の基礎作りに多大な貢献をしたと言えます。
フランスへの留学帰りの渋沢栄一が、明治維新後すぐに実業家とならず、大蔵省で働いたことは運命のいたずらかもしれませんが、会社が活動するための土壌となる、インフラやルールの整備に自ら関与したのは、会社を作る以上に重要なことだったと思います。
そして、会社についても、「合本主義」という独特の考え方を取っていて、(公財)渋沢栄一記念財団のホームページからの抜粋によると、『「合本主義」とは、「公益を追求するという使命や目的を達成するのに最も適した人材と資本を集め、事業を推進させるという考え方」を意味するといえます。』、とあります。会社の利益ではなく、公益を追求することで、事業が発展し、永続する考え方と解釈しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 4.おわりに
----------------------------------------------------------------------
最近は、サスティナビリティという言葉が当たり前のように使われていますが、渋沢栄一の合本主義はまさに、サスティナビリティ経営を標榜している経営手法のように思えます。アメリカが自国第一主義、保護貿易は、サステナブルな世の中を実現出来るのでしょうか?自国だけ良ければいいという考え方ではなく、国が、企業が、そして一個人が、少しでも自分以外にも配慮して、つまり公益を意識して行動する世の中になればと願います。