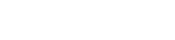vol.209 東証グロース市場に適用される時価総額100億円基準の影響
ビズサプリの久保です。
今年は、梅雨入り後に暑い日が続き、西日本では6月中に梅雨明けし、関東もそろそろ梅雨明けしそうな感じになっています。
都議会選挙が終わり、このメルマガが発行される頃には参議院選挙が公示されます。
トランプ関税だけでなく、ウクライナや中東での紛争の出口が見えず、気になるところです。
今回のメルマガでは、量より質を目指す東証の市場再編策第二弾のお話になります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.グロース上場企業への影響
----------------------------------------------------------------------
グロース市場に上場してから「5年で時価総額が100億円に達しない企業」は上場廃止になるかもしれません。東証によると、この上場維持基準をパブリックコメントに付した後、公表するとしています。(本メルマガ執筆時現在では、まだパブリックコメントは公表されていません)。現状のグロース市場の上場維持基準は「上場後10年経過後に40億円以上」であり、これに比べるとかなりハードルが高くなります。
この新基準は2030年以降に上場後5年経過している企業に適用されます。すでに上場している企業だけでなく、今年上場する企業も2030年には5年経過することになると考えられます。
この100億円は「グロース市場に上場後、時価総額100億円以上に成長した企業の93%は5年以内にこれを実現していた」という実績に基づいて決められたようです(「グロース市場における今後の対応」東証上場部2025年4月22日)。
ということは、5年以内に100億円以上にならない企業はそれ以降も100億円以上になる可能性が低いとみられるということです。東証はこのような企業をスタンダード市場に変更するよう促すようです。ただし、スタンダード市場の上場維持基準に満たない企業は上場廃止になると予想されます。
前出の「グロース市場における今後の対応」(東証)によれば、現状のグロース上場企業では個人投資家中心の株主構成となっており、「機関投資家が入って流動性が確保されるには最低でも時価総額300億円が必要、100億円は本当に最低限のラインである」という意見が得られたとしています。そういう観点からも時価総額100億円基準が出てきたようです。
現状では、グロース市場上場企業約600社のうち約7割の企業が時価総額100億円に届いていません(日経新聞)。また、上場後5年経過しているグロース市場上場企業のうち時価総額100億円に満たない企業は201社あります(東洋経済オンライン)。
なお、経過措置により現行の「上場後10年経過後に40億円以上」はまだ適用されていません。今年の3月末でその経過措置が終了し、その後1年間の改善期間を経て上場廃止となるからです。東証によれば、改善期間該当企業のうちグロース市場上場企業は23社(2025年6月18日現在、全体で114社)あります。
東証は「十分な助走期間を確保」するため、2030年以降に上場から5年が経過した企業に新基準を適用するとしています。新基準未達企業が続出することはほぼ間違いありませんが、この「助走期間」を長くしても、過去の実績からみて時価総額100億円以上の企業が多くなるとは考えにくいです。そのため、新基準未達企業は、一旦スタンダード市場に移行してもらうのがよさそうです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.IPO準備企業への影響
----------------------------------------------------------------------
新規上場時の審査基準は、従来通り「流通株式時価総額 5億円以上かつ流通株式比率 25%以上」であり、この変更はありません。流通株式時価総額5億円が25%に相当するのであれば、時価総額20億円ということになり、流通株式比率が50%であれば、時価総額10億円ということになります。
ただし、上場して5年経過後には時価総額100億円というハードルがあります。このため、上場審査において5年後に時価総額100億円以上になるような事業計画の策定が求められるようになると思われます。
上場審査を通過して無事上場できたとしても、5年後にはこの上場維持基準をクリアすることが必要になります。結局のところ、新規上場を目指すIPO準備企業にとっては、実質上、上場審査基準が変更されたと考えることもできます。
無理してグロース市場に上場しても、そのうちスタンダード市場に変更させられるのであれば、最初からスタンダード市場への上場を目指す、という会社も増えてくるかもしれません。
ただ、少し注意が必要な点があります。スタンダード市場ではコーポレートガバナンス・コードの基本原則、原則、補充原則のすべてが適用されますが、グロース市場では基本原則だけが適用されます。また、グロース市場では上場後3年間はJ-SOXの内部統制監査が免除されますが、スタンダード市場ではその免除はありません。すなわち、上場時のハードルがスタンダード市場の方がやや高いと言えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.上場を支援する企業への影響
----------------------------------------------------------------------
これから上場を目指すスタートアップ企業にはかなり厳しい基準が適用されようとしています。その結果、ベンチャーキャビタル(VC)がこれまで以上に投資先の選別を厳しく行い、1社当たりの投資額が多額になると考えられます。資金規模の小さいファンドは、これまでより投資先が少なくなるため、投資リスクが高くなることもあるでしょう。この点から、ファンドの規模がさらに大きくなるとも予想されます。
創業から上場までの年数が伸びる可能性もあります。これまでは10年程度のファンドの運用期間内で上場を果たして資金回収ができていましたが、運用期間内の投資では成果が出ない可能性があります。このため、ファンドの運用期間終了後、別のファンドに引き継ぐための未上場株式のマーケットも必要になると考えられます。
さらに、これまでのように、年間100社近い企業が新規上場することはなくなるため、引き受け証券会社や、上場支援を行う監査法人やコンサルティング会社の戦略にも影響が出るでしょう。
以上のように、グロース市場の上場維持基準の厳格化はさまざまな影響を及ぼすことになりそうです。
本日もAW-Biz通信をお読みいただきありがとうございます。
ビズサプリでは、上場準備に当たっての内部統制整備、内部監査のアウトソーシング、常勤監査役等のご紹介や、上場会社に対するTOBやMBOを含むM&Aに関わるご相談をお受けしております。
お気軽にご連絡いただきますようお願いいたします。