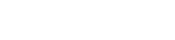vol.206 スポーツ不正とルールと会計士
ビズサプリの三木です。
フジテレビの騒動やトランプ大統領の関税騒ぎにかき消されてしまった感はありますが、2025年3月にノルウェーのスキージャンプチームで大きな不正が発覚しました。
今回のメルマガは、この不正のニュースを見て感じたことを書かせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.競技用スーツの不正
----------------------------------------------------------------------
2025年3月にノルウェーで行われたノルディックスキー世界選手権で、男子ジャンプの個人ラージヒルの競技の前に一本の動画が拡散されました。それは、ノルウェーのチームが競技用スーツに不正加工をしている様子を捉えた動画でした。しかもコーチが同席しており、組織ぐるみの行為を示唆するものでした。
スキージャンプではいかに風をうまくとらえるかで飛距離が変わるらしく、スーツが大きいほど有利になるため、厳密にスーツの寸法が決められています。2021年には日本の高梨沙羅がスーツの規定違反で失格処分となる事件があり、競技後に測定する方法の是非や、計測者による誤差が無かったのかなど、多くの議論を引き起こしました。
件のノルウェーチームは疑惑があるまま個人ラージヒルの競技に臨みましたが、競技終了後に検査官がスーツを検査したところ不正改造と認定されました。ちなみに、日本の小林陵侑が繰り上がってメダル獲得となっています。
競技ですからスーツの規定に本来曖昧さは許されません。しかし、現実的には完璧なルールというのはまた難しいようです。例えば素材の制限をしても想定していなかった新素材が登場したり、体重や体格を基準にルールを決めても温度で体格自体が変化したり・・・・・・といった具合です。競技者やチームとしてはギリギリを攻めることで良い記録を狙うのは当然で、そのせめぎあいは宿命と言っても良いでしょう。高梨沙羅の場合は(運営側の問題もあったにせよ)攻めすぎたということであり、ノルウェーチームの場合は明らかに不正という領域にまで踏み込んでしまったということでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.ルールとプリンシプル
----------------------------------------------------------------------
スキージャンプとは全く違う話ですが、ここ10年ほど内部監査や内部統制、そしてガバナンスや会計に関する規範はルールベースからプリンシプルベースに変わってきました。ルールとは「制限速度50キロ」などの具体的な決めごとであり、プリンシプルとは「安全な速度で運転する」といった考え方を示す規範です。ルールのほうが見解相違もなく明確ですが、①ルールを形式的に守るだけで目的が意識されない、②想定外に対応できない、③皆が抜け穴を探すといった弊害が目立ってきたためプリンシプルベースの規範が増えてきました。
プリンシプルベースには曖昧さがつきもののため、客観的に説明できる判断プロセスを持つことと、判断内容への説明責任が必要です。収益認識基準にかかる判断を監査法人と協議するのも、コーポレートガバナンス・コードのComply or Explainの考え方も、J-SOXの内部統制報告書で評価範囲の決め方を説明させるのも、判断プロセスの明確化や説明責任を反映したものと言えます。
もっとも、プリンシプルベースの持つ曖昧さとは相いれない世界はあります。刑法を曖昧な基準で運用されると困りますし、「制限速度を超えてても安全」「制限速度以下でも危険」といった判断を是々非々で行われると警察は好きにスピード違反を取り締まれることになり、権力の濫用にもつながります。スキージャンプなどのスポーツではルールベースで曖昧さを排除するべきですが、例えばスーツの事前審査といった判断プロセスを入れるなど、プリンシプルベースから学ぶべき点もありそうな気がします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.会計士はアーティスト?
----------------------------------------------------------------------
ところで、この仕事をしていると「(公認)会計士と税理士って何が違うの?」と良く聞かれます。どちらも会計の知識を持ち、会計士は業績を示す会計を担い、税理士は税金計算を専門としています。ただ個人的には、昔に知人から言われた「会計士はアーティストで、税理士は法律家」という性格の違いが大きいと感じています。
税務の世界は判断の違いにより納付税額がダイレクトに変わります。このため税法には膨大な細則があり、ルールベースで動いています。このルールとは原則として法律と判例です。課税はルールに基づいて公平でないと不平不満が出ますので、あまりプリンシプルベースには向きません。
一方で会計士が担う会計は、アーティストというと言い過ぎかもしれませんが、業績や財政状態をいかに決算書で表現するかという大命題があります。そして、そのための規範として様々な会計基準がありますが、実は会計基準には解釈の幅が大きく、税法のようにはっきりと白黒つけないものが多くなっています。その幅の中で業績をいかにフェアに表現するかが会計士の仕事です。(そもそも会計基準は法律ではなく、公益財団法人である財務会計基準機構が決めています)
こういう違いから、会計士の仕事はプリンシプルベースのものが多く、税理士の仕事はルールベースのものが多いといえます。こうした性格の違いが「会計士はいい加減」「税理士は細かい」といった印象にもつながっているように思います。
ルールベースとプリンシプルベースにはそれぞれメリットとデメリットがあり、向き不向きがあります。ルールベースの仕事でプリンシプルベースの判断をすれば「いい加減なやつ」になり、逆なら「形ばかり気にするやつ」になります。ノルウェーチームのスーツ不正は論外としても、ルールとプリンシプルそれぞれの性格を理解して、場面ごとにうまく使い分け、自身も適応していく必要がありそうです。
本日もAW-Biz通信をお読みいただきありがとうございました。