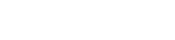vol.202 責任とは何か?
ビズサプリの三木です。
昨年2024年は10月に日本の衆議院選挙が行われ、自民党が大きく議席を減らしました。この結果を受け、選挙対策委員長であった小泉氏は責任を取って辞表を提出した一方で、石破首相は責任を持って職責を遂行する意思を表明しました。責任という言葉の使い方が無責任ではないかと思った出来事でした。
そして、このメルマガを書いている2025年1月27日、中居氏の騒動からの不祥事に揺れているフジテレビが2回目の記者会見を行い、会長及び社長がこうした事態を生じさせた責任を踏まえ辞任する旨が発表されました。
今回のメルマガは、分かっていそうで分からない「責任」について考えてみます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.「責任」が使われるシーン
----------------------------------------------------------------------
プライベートでも仕事でも「責任」という言葉は実によく使われます。いくつか挙げてみます。
・登山家:登山の危険は自己責任
・会社の上司:俺が責任を取るから自由にやれ
・政治家A:責任を取って辞める
・政治家B:責任をもって続投する
・モラハラ夫:家庭を維持するのはお前の責任!
当社の仕事だと、内部統制や内部監査の支援、あるいは不正や不祥事の対応といった様々な場面で「責任」という言葉に触れますが、概ね以下の3つのパターンで使われています(私の主観です)。
・遂行責任(主体性を持ってやり抜く)
・賠償責任(問題が生じた時に自分が賠償する)
・承認責任(問題があれば管理者としてペナルティを負う)
政治家が責任をもって続投する場合は①で、引責辞任する場合は②(自身の報酬と社会的立場を返上することで失敗の賠償とする)ということになります。
登山家の場合は遭難時の救助費用は自費で賄う意味で②、モラハラ夫は①です。
会社の上司は①と③の組み合わせです。問題が生じた時に対策の主体として踏ん張ると共に、管理者として例えば減俸などのペナルティを覚悟する、という意味合いで使われます。
「責任」という言葉は便利なので多用してしまいがちですが、①②③でその内容が異なります。言ったほうは③のつもり、受け取ったほうは①のつもり、といった食い違いがあると「責任を取ると言ってたのにあの対応は無責任だ!」といったトラブルにもなります。失敗が許されないシーンでは、「責任」がどの意味で使われているか、意識することが必要そうです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.ジャーナリスト安田氏の拘束の場合
----------------------------------------------------------------------
2015年、ジャーナリストの安田純平氏はシリアで武装勢力に拘束されました。その後、実に3年に渡り拘束された後に解放され、2018年にトルコを介して無事帰国しました。
無事に帰国できたのは何よりも喜ばしいことですが、考えてみるとこの場合の「責任」は実に複雑です。
安田氏はかねがね、
・危険地でも行くのがジャーナリストの遂行「責任」である
・場合によっては死という自己の賠償「責任」を負う覚悟はある
・拘束などの事態での邦人保護は政府の賠償「責任」である
と主張してきました。
ジャーナリストとしての業務遂行責任は理解できます。また、安田氏はフリーのジャーナリストで、最悪は死亡という結果を受け入れることは個人の覚悟として可能でしょう。しかし、邦人保護のための費用を自身で賄うことはとても不可能です。
勇敢なジャーナリストがいるからこそ我々はお茶の間で世界情勢を知ることができています。だからこそ受益者である我々が、税金と政府を通して、邦人保護の責任の一端を負う構造も成り立ちます。しかしながら、可能な限りの安全対策を行って乗り込むジャーナリストに邦人保護を行うのは理解できたとしても、いざとなれば政府が税金で助けてくれると安易に危険地に行ってしまう観光客に税金を投入するのには忸怩たる思いを抱く人も多いと思います。このように、賠償責任が成り立たない場合にはモラルリスクが生じやすくなります。
モラルリスクが発生してしまうと、全体として適切な業務設計が難しくなります。旅の恥は掻き捨てでレンタカーだと運転が荒くなるといった現象と同じです。企業の業務設計時にはこうした点も考慮に入れて設計を行っていきますが、邦人保護のように国民としての権利に関わるような内容だとそうもいかず、良い解決策が無いのが現状です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.英語では
----------------------------------------------------------------------
日本に比べると何かとドキュメント化する傾向が強い英語圏では、「責任」についても複数の単語が使い分けされているようです。まずは以下3つがあります。
・遂行責任 Responsibility
・説明責任 Accountability
・賠償責任 Liability
それぞれの言葉は今日の日本でも説明されれば意味は通じますが、単語としてそもそも分けられているということは歴史や文化に根差していることの証明でもあります。日本で「責任」という言葉が「無責任」に使われがちなのは、こうした深い使い分けが輸入品であることと無関係ではないように思います。
特に前述した日本での使われ方①②③では、Accountabilityが登場しませんでした。サステナビリティやCSRなど開示制度が拡充されても肝心の中身が横並びから脱却できない状況や、日本人は概してプレゼンが下手と言われたりすることを思い起こすと、説明ということに対する意識の差が文化レベルで存在していることと関係しているのかなと感じます。
その他に責任に近い言葉として、DutyやObligationといった単語もあります。これらは「責任」というより「義務」を指す言葉で、ペナルティの意味合いはありません。
Dutyは、自分の判断で実施可否を決められる比較的小さな義務に使われることが多く、Taskに近いニュアンスがあるようです。対してObligationは、法律や会社・社会のルールとして実施しなければならないやや重い義務を指すようです。
ちなみに、間もなくバレンタインデーですが、「義理チョコ」にはObligationを使います。
2018年、ゴディバは「日本は義理チョコをやめよう」と広告を出しました。これに対し、ブラックサンダーを販売する有楽製菓は、「日頃の感謝を伝えるきっかけとして義理チョコ文化を応援いたします」とツイッターで反応しました。
実は真逆に見えて、両社の言っていることに大して違いはありません。社会的な義務=Obligationとしてのチョコは止めよう、でも謝意を示すために自分が必要と考える=DutyのチョコはOKということだったそうです。
「責任」にせよ「義務」にせよ、言葉というのは独り歩きします。重要な場面では、無責任に使いがちな言葉をよくよく考えて使う必要があると思わせる出来事でした。
本日もAW-Biz通信をお読みいただき、ありがとうございました。