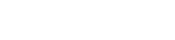vol.214 温暖化と人の思考
ビズサプリの三木です。
2025年の夏は記録的な猛暑でした。外を歩いて取引先に着くころには汗だくで、エアコンが体を冷やしてくれるまでは思考力が働かないことも多々ありました。今回は、「温度と思考」関係について考えてみたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.暑さは不幸、寒さも不幸
----------------------------------------------------------------------
言うまでもなく、炎天下では人間の思考力や集中力は鈍ります。40度前後を連発した今年の夏、たとえば建設現場などでは、暑さ自体による熱中症リスクはもちろん、暑さによる集中力低下が安全管理に与える影響は無視できなかったと思います。暑いとイライラしがちなこともあり、猛暑による業務効率や幸福度の低下は皆さんも体感されたのではないでしょうか。
一方、寒さも思考力を奪います。私の趣味はスキューバダイビングですが、今年の夏は関東近辺の海が意外と冷たく、なんと8月のお盆に水温が17度という日がありました。黒潮大蛇行が終わった影響らしいですが、17度では夏用の保護スーツだと体の芯まで冷えてしまい、「寒い」以外のことが考えられなくなります。陸は猛暑、海は冷水―まさに「適温のありがたさ」を思い知らされた夏でした。
2年ほど前にNHK「クローズアップ現代」で紹介されていましたが、住宅内の温度が脳の健康に影響するという研究もあります。寒すぎる環境では睡眠の質が低下し、毛細血管が収縮して血流が悪くなり、それが長期間蓄積すると脳が萎縮、すなわち老化が早まるという仕組みのようです。
その時々の思考力・判断力にせよ、幸福度にせよ、長期的な脳の機能維持にせよ、「適温」が非常に重要なファクターであることは間違いありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.心の温度差の広がり
----------------------------------------------------------------------
最近、地球温暖化が人間の感情にどのような影響を及ぼすかについての記事を目にしました。そのデータソースとなっていた「Unequal impact of rising temperature on global human sentiment」という論文では、157か国・10億件以上のソーシャルメディア投稿を分析し、気候状況との関連を調べています。いわば「気温が人の心にどう影響するか」を世界規模で検証したものです。
この研究によると、気温上昇が幸福度を低下させるのは予想どおりですが、その影響の大きさは低所得国ほど顕著で、つまり貧困層が不均衡に心理的負担を強いられていることが示されました。経済的格差の拡大による社会の分断は世界各地で問題になっていますが、この研究で示されたように温暖化による心理的影響にも格差があるとすれば、知らず知らずのうちに経済的な分断が感情的温度の格差にまで広がっていきかねません。
ここ数年の猛暑で、私たち自身も暑さが精神的健康や幸福度に影響することを実感しています。温暖化は気候や経済の問題として語られがちですが、今後の政策を考えるうえでは、精神的健康や幸福度、すなわちQOLの問題もクローズアップされてくるかもしれません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.思考環境の工夫
----------------------------------------------------------------------
猛暑だった今年の夏、ある取引先の会議室でエアコンが不調な時期がありました。部屋に入った瞬間から空気が「むわっ」としていて、参加者がどうしてもイライラしてしまいがちですし、議論もどこか切れ味を欠く感じがしてしまいました。また、過去に伺ったある会社では、経費節減のため照明とエアコンを相当に抑制しており、薄暗い中で社員が腕まくりをして仕事をしており、思考環境が犠牲になっていると感じました。
私たちはつい「頭の中の問題は頭で解決できる」と考えがちですが、実際には身体が置かれている環境が思考の効率や感情の安定を大きく左右しています。不機嫌や疲労、暑さなどによる誤った判断を避けるためにも正しく考えるための環境づくりが必要です。
例えば、会議の議題が重い内容のときはエアコンのエコ設定(28℃)にこだわらない、猛暑など天候理由での在宅勤務を広く認める、在宅勤務では快適な室温を保てるよう補助を検討するなど、少し経費をかけても十分にリターンが見込める工夫は取り入れていきたいものです。
思考環境の確保は、単に従業員満足度を高めるためではなく、正しく考えるために必要な条件でもあります。温暖化が進む今こそ、思考の場をどう守るかにも意識を向けたいものです。