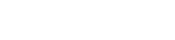vol.212 多忙な中で「休む」
皆様、こんにちは。ビズサプリの辻です。
今年の夏は、また一段と酷暑でしたね。私の趣味はマラソンなのですが、今年の夏のトレーニングは大変苦労しました。8月31日に北海道マラソンを走りましたが、夏の疲れなのか調子が上がらず「完走」はしましたが、私自身としては惨敗のレースとなりました。また秋のマラソンシーズンに向けて立て直しです。
このように仕事の余暇に「趣味」を持つことは、心身ともにリフレッシュでき、仕事にも良い効果があるというのは経験上も思っているところですが、休暇が与える影響を調査した結果が、ハーバード・ビジネス・レビュー(以下、HBR)(2025年9月号)「戦略的に休む」で特集されていましたのでご紹介したいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.どのような余暇の過ごし方がよいのか
----------------------------------------------------------------------
仕事でクタクタになって帰宅した後、どのように過ごしたいでしょうか。そのままソファーに倒れ込み、テレビをつけてスマホのSNSをなんとはなしに眺めてゆったりとしたいという方が多いのではないでしょうか。
ある研究の分析によると、一人で余暇を過ごす場合、「昼寝、テレビ視聴、SNSの利用」といった受動的な活動よりも、運動や趣味といった能動的な活動の方が大きな満足度を示し、能動的な活動に時間を割いている人の方が人生に対する満足度が高いという結果が出たそうです。もちろん、時にはぼんやりしたり、リラックスすることは大切ですが、そればかりだとひょっとしたら人生の満足度を下げてしまっているかもしれません。ちなみに、一人で活動をする場合、満足度が低い活動ワースト3は、SNS、飲食、ボランティアで、満足度が高い活動ベスト3は、趣味、運動、スピリチュアルな活動だそうです。
別の研究では、一人で余暇を過ごすのと、人と過ごすことで満足度がどのように変化するかを調べていました。この結果、どのような活動であっても一人で過ごすよりは、誰かと体験を共有すると満足度が上がったそうです。特に、飲食やゲームはその変化が大きく、「店を予約する」「時間を約束する」といった手間をさし引いて余りある満足度があるようです。私の趣味である「運動」も、一人よりは仲間と一緒にやった方が満足度が高くなっています。確かに、ラン友と一緒に走る方が断然楽しいものです。(ラン後のビールも最高です。)
みなさまには、仕事以外に余暇を過ごす友人はいらっしゃいますか。仕事以外の「仲間」を作ることは、人生の満足度を上げるうえで大切なことのようです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.良いと思われるものと夢中になれるもの
----------------------------------------------------------------------
運動がいいからといって、好きでもないのに運動を始めても満足度は高くなりません。当たり前のことですが、研究結果においても、一般的によいと思われる活動よりは、自分自身が楽しいと思えることに余暇を当てた方が満足度はかなり高いと出ているそうです。つまり、誰かの余暇の過ごし方をマネするのではなく、自分自身が能動的に活動をして「楽しい」と思えるものを探した方がよさそうです。
ただ、難しいのは、一つの活動に割く時間が多くなるほど、その増分が満たす満足度は次第に低下していき、1つの余暇の活動に充てる時間が週7時間を超えると、むしろ満足度が低下していくとのことでした。夢中になりすぎて、それだけに没頭すると楽しくなくなってしまうようです。
私のマラソントレーニングにかける時間は週7時間ぐらい。これ以上練習をするとダメなようです。「週に2回ぐらいは走らず会食の予定が入っているのはちょうどよいバランスなのか」と妙に納得しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.休暇の必要性
----------------------------------------------------------------------
働き方改革が進む中で、企業も「休むこと」の重要性に注目し始めています。そもそも人間の体は休みをとらずに絶えず働けるようにはできておらず、そこで無理を強いられると「燃え尽き症候群」(バーンアウト)になってしまいます。現にそういう会社の離職率は大変高く、当然会社の雰囲気は悪くなっていくものです。加えて、「休みが悪」という雰囲気があると、休憩をしていることを隠そうとする傾向が出てくるそうです。HBRでは、その例として「トイレでソーシャルメディアのサイトをスクロールしたり、働いているフリをしたり、バーチャル会議の最中にオンラインショッピングをしたりする」を挙げています。誰でも多少の心当たりはあるのではないでしょうか。コロナ以降リモートワーク比率が高くなると、このような「隠れて行う休憩」の弊害も大きくなっているように思います。
「隠れて行う休憩」を蔓延らせないためにも、休みを適切にとることは良い仕事をするうえで大切なことである、という共通認識を持つ必要がありそうです。最近では、昼寝を推奨したり、リラックススペースを設けたりするなど、休憩を積極的に促すことで集中力を高め、生産性の向上につなげようとする取り組みも広がっています。
さらに、短い「休憩」ではなく、仕事を長期に離れて新たな挑戦や経験を積むような「サバティカル休暇」をとり、その経験で知識や視野を広げるという取り組みもあるそうです。例えば、6か月間休暇をとって聖地巡礼をするとか、3か月かけて仕事とは異なる分野で本を執筆するとか、リゾートのレストランの厨房で修行をするといった通常の仕事とは切り離された過ごし方をするといったことのようです。このような経験は、自身の働き方を見直すきっかけとなり、とくに燃え尽き症候群からの回復には有効だそうです。とはいえ、このような長期休暇はまだまだ一般的には広がっておらず、取得する側にも大きな負担や責任がありそうですが、国内の会社でも「浮世離れ休暇」といって勤続5年を迎えた社員に対し、1ヶ月連続の有給休暇を取得できるといった取り組みもあるそうです(ITmedia ビジネスオンライン2023年5月12日号)。休暇のネーミングも面白いですよね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 4.休むか全力投球か以外の選択肢
----------------------------------------------------------------------
ここまで「休む」ということについて書いてきましたが、仕事を休むのではなく、一時的に仕事に対する優先順位を変えるということもあります。子育てや介護、自身の疾病等で仕事に全力投球できない場合に仕事に対する優先順位を下げるけれど、仕事を続けることでキャリアの中断を避けるといったことは想像しやすいかと思います。ただ、HBRで紹介されているのは少し違っていて、例えば「趣味で行っている演劇で主役に抜擢されたため、そのチャンスを活かしながら仕事も続ける」といった事例でした。具体的には、「日中にリハーサルに参加しなければならない4週間は特例的なスケジュールで仕事をし、その後公演が始まると、もっとも緊急かつ重要な仕事にはきちんと対応しつつ、優先順位の見直しと権限委譲を通じて勤務時間を調整した」とのこと。それによりその人の仕事への活力が大いに増して、その後も継続してよい仕事をし続けたとの事です。このような権限移譲ができるということは、業務の透明化につながり、そしてお互いの信頼関係も必要ですから、きっとこの職場は環境もよいのでしょう。
さらにHBRでは、「製品責任者は今後4か月間の一時的後退期(仕事の優先順位を下げる時期)に入ります。副責任者達にはストレッチ課題が課され、レベルアップの準備ができていることを示すよい機会となるでしょう。ワクワクしますね。」という会話が交わされるようになると、組織の柔軟性、透明性、コミットメントも進むようになるといっています。
我が国でも「働き方改革」で有給休暇の取得が推奨されるようになってきました。「そんなこと言っても休めないよ」という原因が本当は何であるか、振り返ってみてはいかがでしょうか。