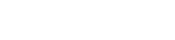vol.207 日本とイタリアの近似性から、今後の地方創生を考える
皆様、こんにちは。アカウンティングワークスの花房です。
前回の私のメルマガでは、2025年1月時点のコメの物価指数が前年同月と比べて、約7割の上昇を契機とした、令和の米騒動と食料政策というテーマで、日本の食料政策に言及しました。(参考:メルマガvol.203 令和の米騒動と食料政策「https://biz-suppli.com/newsletter/1076/)
そして、コメと言えばおにぎり(私だけかもしれませんが)、おにぎりと言えば海苔を連想するのですが、この海苔の価格も、近年上昇を続けています。これは、事情はコメの不作に近いかもしれませんが、「植物プランクトンが異常発生し、海の中の栄養が足りなくなっている。冬の高水温でクロダイやアイゴの動きが活発になり、海藻を食べてしまう。養殖業者が減っていることもじわじわと響いている」(5月19日付日経新聞『春秋』より抜粋)、ことから、海苔の生産量はピークの1990年代には100億枚/年であったが、直近では50億枚/年、に減少していることによるものです。
今回は視点を変え、地方創生にも繋がるであろう、一次産業のあるべき姿について考えてみたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.食の展示会の実態
----------------------------------------------------------------------
先日、クライアントの方と東京ビッグサイト(東京国際展示場)で開催された食の展示会を見てきました。行きのゆりかもめで明らかに企業関係者ではない方が多く、東京ビッグサイト駅で降車し、同じイベントに向かう方が多数いらっしゃいました。
皆様食の展示会が目的地だったのですが、当日でもこの展示会は参加費無料で入場することができ、展示会場では様々な食品、お酒などの飲料の試食・試飲が出来ることから、一般の入場者も多いようです。実際、展示会に出展している事業者の方に聞くと、体感ではありますが、実に6割は少なくとも、商談目的ではない方が来ているとのことでした。それだけ、食に対する皆さんの関心は高いという証左でもあります。
この食の展示会に出てみて感じたことは、世界中にはまだまだ知らない食材、料理、お酒等の飲料が如何に多いのか、ということでした。世の中には、ファストフードやナショナルブランド、OEMブランドのメーカーがある一方で、素材や生産過程、美味しさにこだわった生産者、製造者の方もいらっしゃるという事実です。
コモディティ化、デジタル化が進む一方で、逆にとんがったもの、アナログなものが見直される傾向にあります。時代は「振り子」と言いますが、昔流行ったものがまた脚光を浴びる等ブームは繰り返す(但し全く同じ形ではなく、その時代に合った洗練された形で)と言いますが、人は、現在そこにないものを常に求めて生きているように思います。その意味で、古き良き時代のものを今風にアレンジしていくことが、これからの一次産業のあるべき未来、そして地方創生に繋がるのではないかと考えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.日本と近いイタリア
----------------------------------------------------------------------
日本とイタリアの共通点はいくつか挙げられます。まず、国の成り立ちの歴史で言うと、日本は神武天皇以来、世界最古と言われる王朝(皇室)の流れを汲む国ではありますが、実際には地方に様々な多くの「国」があり、それが江戸時代に統一されて明治維新(1868年)を経て、今の日本が作られましたが、イタリアも元々独立した小国が統一されて(1861年のイタリア王国の成立)、一つの国になったという意味では、近代化の歴史が似ています。
その要因として大きいと考えられるのは、日本とイタリアはいずれも南北に長く、また国に占める山地や丘陵地の割合は約75%と言われていますが、イタリアも約7割が山岳・丘陵地で. あり、国土に占める平地の割合は日本と似ていると言えます。
そして、イタリアには、日本と同じように春、夏、秋、冬の四季があるというのも特徴です。この南北に長いこと、四季があること、また山も海もあることから、地域により、時期により採れる農産物や魚介類、畜産物が異なることは、食の多様なバリュエーションを生み出す要因となっています。
私が最近読んだ、『イタリア食紀行 南北1200キロの農山漁村と郷土料理 大石尚子 著』、という書籍があります。ここでは、今後の日本の食に関する、そして地方創生に繋がる方向性として有用な、様々な示唆に富む内容が盛り沢山なのですが、最近日本でも言われるようになった、アグリツーリズム、スローフード、地産地消は全て、イタリア発祥ということでした。
アグリツーリズムは、イタリアでも日本と同様に、都市部への人口流出が進んだことから、農村が過疎化し、地方経済が衰退してきたことに対して、農業そのものを観光資源として収入源とするため、農家が自身の家の一部を観光客に提供し、食事も自分の畑や地域の港からとれた新鮮な魚介類、近隣の畜産物等を食材とした地元の料理を提供するスタイルが原型のようです。
そして、アグリツーリズムの土壌があったことから、1980年代にファストフードに対抗する形で、生産者や健康、そして環境に配慮した食事を重視するスローフード運動に繋がったと言われています。スローフード協会のスローガンに、「おいしい・きれい・正しい」と言うのがありますが、特に『正しい』と言うのは、生産に関わる者すべてに適正な賃金と労働環境を提供することで、生産者を守り、伝統的な手法を絶やさず、地域の伝統やローカルフードを守ることに繋がっています。
そしてこのことは、唯一無二のその地域でしか生産できない食材を生む出すこととなり、パルミジャーノ・レッジャーノ(世界三大チーズ)や「プロシュート・ディ・パルマ」(世界三大ハム)のような、世界的に有名なブランド食材の産地が至るところにあります。イタリアはフランスと並び、食だけでなくアパレルでも高級ブランドを擁する国ですが、ブランド化をすることで付加価値が高まり、生産者やメーカーなど、そこで働く地域の人々を豊かにすることになります。
私の個人的な意見としては、イタリアのように、地方発の世界的ブランドを数多く育てることが、これからの日本の目指すべき方向性の1つだと考えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.「ほうれんそう」と絡めて(おまけ)
----------------------------------------------------------------------
私は今年で、社会人になってから28年目に入ります。当時のビジネス用語で、部下から上司へコミュニケーションを図る用語である、「ホウレンソウ」(報告・連絡・相談の頭文字)を行うことを心得るように教えられました。今でもその用語は、ビジネスにおいては一般的ですが、そのファミリーがいるということを最近知りました。
まず、「チンゲンサイ」。これは、チン=沈黙する、ゲン=限界まで言わない、サイ=最後まで我慢、を意味し、確かに今の時代ではその傾向があるように思いますが、使い方としては、「チンゲンサイになってない?何かあれば相談してね」のように部下に言うようです。
また、「オヒタシ」、というのもあるようです。これは、「オ=怒らないで、ヒ=否定せず、タ=助けの手を差し伸べて、シ=指示する」用語とのことで、上司は、ホウレンソウを受けたからには、オヒタシのような対応を意識しなければならない、ということになります。
そして、止めは「コマツナ」。これは、『困ったら(コマ)、使える人に(ツ)、投げる(ナ)』という用語で、もはや駄洒落のようになっていますが、このようなユーモアも時には必要なのでしょうね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 4.おわりに
----------------------------------------------------------------------
本日は、私が食とイタリア(まだ行ったことはありませんが)が好きということもありますが、日本の食と一次産業を考える上で、1つのヒントとなると思い、執筆しました。ただ、これはアイデアの1つであり、本当に地域創成をしたいのであれば、実際に地域の住民の方々が危機感を感じ(実際、イタリアでアグリツーリズムやスローフード運動が始まった時期は、危機感を感じていたようです)、本当に復興したいと本気にならなければ、実行できないと思います(『言うは易し、行うは難し』)。
アカウンティングワークス株式会社では、実効性のある事業計画や、人材マネジメントに行かせるエンゲージメント調査など、幅広く様々な経営・会計コンサルティングを行っております。初回ご相談無料ですので、お気軽にご連絡下さい。https://acwks.com/
本日もAW-Biz通信をお読みいただきありがとうございました。