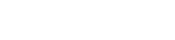vol.204 改めて、ガバナンス
皆様、こんにちは。ビズサプリの辻です。
つい先日新年を迎えたと思ったら、気がつけばすでに1年の4分の1が過ぎ、年度末が目前に迫っています。初夏のような陽気になったかと思えば、冷たい雨や雪が降るなど、寒暖差の激しい日が続き、体調管理の難しさを感じる日々です。
さて、最近12月決算の上場会社が増えてきたため、3月後半になると株主総会シーズンがやってきます。最近ではアクティビストによる単に短期的な株主還元を求めるだけでない株主提案も多くみられるようになりました。株主は会社のオーナーであり、そのオーナーとの直接対話の場である株主総会は、コーポレートガバナンスの観点からは重要な「場」として捉えて対応をする会社も増えているように思います。今日は改めてガバナンスについて考えてみたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 1.株主総会に向けて
----------------------------------------------------------------------
2024年6月株主総会シーズンの株主提案数は113社、機関投資家による株主提案数は59社と前年61社に引き続き高水準で推移したそうです(大和総研 「アクティビスト投資家動向(2024年総括と2025年への示唆)」)。
このような株主提案への賛成率は提案内容によってもばらつきがありますが、まだまだ低いのが現状です。
ただ、低PBR企業、不祥事企業、政策保有株式を多く有する企業に対してはISS等の議決権行使助言会社の基準もあり、機関投資家を中心にトップの選任議案に反対票が集まり、賛成率が80%未満となるような企業がTOPIX500の約1割の53社となったそうです。これは機関投資家の目線がかなり厳しくなっている結果と思います。
低PBR企業を脱するためには「攻め」のガバナンスが重要であり、大きな不祥事を起こさないようにするためには、「守り」のガバナンスが重要となってきます。どちらが欠けていても企業価値を持続的に向上させることはできません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2.攻めのガバナンスの本音
----------------------------------------------------------------------
日本はガバナンス後進国と言われてきました。戦後復興の過程では株の持ち合いのもとで株主の存在をあまり気にせずにいて、それでも高度経済成長期には企業業績は好調でした。しかしバブル崩壊後の経営環境の変化に対応できず、様々な分野で日本の相対的な順位は下がり続け「失われた30年」と言われていることは皆さんご存じの通りです。
そして失われた10年、20年といわれる中、企業が自らの力でガバナンス改革が一向に進まないことに業を煮やして2015年のコーポレートガバナンス・コードが策定され、その後も金融庁、経済産業省、東京証券取引所から多くのガイドラインや実務指針が公表され「国主導」でのガバナンス改革が行われて続けています。少し情けない話ではありますが、海外投資家の資金も流入し、2024年に株価はやっとバブル後の最高値を更新したのは、このガバナンス改革のお陰であるという意見も有力です。
このガバナンス改革で強調されたのは攻めのガバナンスで、2021年の改訂されたコーポレートガバナンス・コードではリスクテイクが強調されています。
具体的には、「取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、・・・経営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援すべきである。また、経営陣の報酬については、・・・健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである。」(【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】)と記載されています。
つまり、リスクテイクを支える環境整備とリスクテイクのインセンティブとしての報酬制度の確立が取締役会の主要な役割ということです。
このような役割を果たすには、経営陣の提案に対して独立・客観的な立場で多角的かつ十分な検討するために社外取締役の役割は非常に重要とされています。
ただ、社外取締役だけが頑張っても執行側が実行しなければ意味がありません。結局のところ、執行側の考え方次第というところも大きいように思います。
社外取締役がいくら意見したとしても執行側にその意見が響き、実行してもらえなければガバナンス改革は進みません。
ここで社外取締役が、企業の歴史や文化を無視してスタンドプレーをしたところでこれもうまくいくはずがありません。
自身を規律する仕組みであるガバナンスについて正しい理解がある経営者がいて、そのような経営者を監視監督する社外取締役が選任され、より良いガバナンスを確立して、次の適切な経営者を選ぶといったループがないと攻めのガバナンスはうまくいかないと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3.守りのガバナンスは重視されていた?
----------------------------------------------------------------------
守りのガバナンスとは、企業価値の毀損を最小限にするためのガバナンスです。
「日本では以前はリスク管理や内部統制といった「守り」のガバナンスに主眼が置かれていたが、コーポレートガバナンス・コードでは「攻め」の ガバナンスに重きが置かれている」といった言われ方がされています。
確かに粉飾決算などの不幸などを契機に整備された「財務報告にかかる内部統制報告制度(J-SOX)」が制度化され、この制度対応に追われたこともあり、このような言われ方をするのかもしれませんが、本当にこれまで守りのガバナンスが重視されていたのでしょうか。
日本を代表するような企業で繰り返し起こる品質不正、ガバナンス先進企業といわれていた会社で起きた多くの不祥事、また不祥事が生じたときの自浄作用の乏しさ(ものが言えない雰囲気、上司の指示だから仕方がない)等を見る限り、適切なリスク識別や内部統制の整備といった守りを万全にしていた、とはいえないのではないでしょうか。
筆者が不正を起こした会社に不正調査や内部監査で業務を実施すると見えてくるのは、現場任せのリスク対応、コストセンターである第2線の軽視、性善説を前提とした脆弱な内部統制(とその状況の放置)といったことがほとんどです。
そして不祥事が起きるまでそのような状況が危機感をもって経営陣に伝わっていません。
このような状況を見ると、守りのガバナンスを重視していたのではなく、建前で守りのガバナンスを重視していることにしていたのではないかと思います。コンプライアンス重視といいながらパワハラを黙認する職場、ルール遵守を言いながら無理な納期や開発スケジュールを要求する上司、「できない」といわないことが評価される風土、まさに建前の守りのガバナンスのメッキがはがれてきているのではないでしょうか。
「守りのガバナンス」が機能しないと企業価値の毀損が一気に進みます。積み上げてきた評判も信頼も失うこととなります。建前の怖さについて、元厚労省の事務次官で郵政不正事件で逮捕され、その後特捜の証拠捏造などが発覚し無罪確定を勝ちとった村木厚子氏は、自身の経験踏まえた著書で次のように指摘しています。
『建前と本音の使い分け方式をやっているとなぜできないのかを説明せずに済むので、なぜできないのか、どうしたらできるようになるのか自ら問うチャンスを逃します。外には遵守しているとうそをついているので、外から叱ってもらうチャンスも逃します。ほかの組織も建前と本音を使い分けているにちがいないと油断しているうちに、自分以外はみんな遵守できる状況になっていたということになりかねません。』
建前でコンプライアンスを考えていると守りのガバナンスで大きく後れをとり、思い切った攻めもできなくなっているかもしれません。
ビズサプリグループでは、「守りのガバナンス」を通じた数多くのご支援を実施しています。お気軽にお問合せください。
AW-Biz通信をお読みいただき、ありがとうございました。